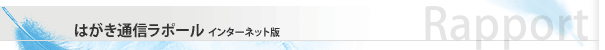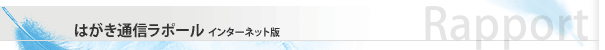2007�N12��25�� |
|
 |
�@��T���j�ߌ�s���̃z�e���ō��N�x�́u����܁v�̔��\��s���܂����B�ȉ��A��Җ�����N�ɂ܂���b�c�B
�@
�����m�̂��Ƃ����N�́A���E���嗤�ō���̍ŔN���L�^�ێ��҂Ƃ��Ă�荡��G���F���X�g��x�m�R�̐��|�����Ƃ��čL���m����Ⴋ�o�R�ƁB�����͎�Î҂̎c�s���ƑI�l�ψ����̖l�̈��A�̌㓯�N�̌y���ȃg�[�N�V���E�̂ق��A��N�̎�Җ�c�G������⌳����b���r�S���q����̂��j���̌��t�������ȂǁA���͑傢�ɐ���オ��܂����B
�@
���̖�A���Ɓu�T���V���v�̋L�҂���d�b������A�����A�ڂ́u�����v�łƂ肠����q���c�g����ɂ��Ă̎�ވ˗��B�������ɉq������Ɩl�Ƃ́A80�N��ȗ��u��w���v�v�̐ϋɓI���i�҂Ƃ��Ă̝፧�̒��������̂ł����A������A���Ȃ����Ă͍����̖�����͐��܂꓾�Ȃ������킯�ł�����A�l�͉��������߂������ɏP��ꂽ����ł��B
�@
����N�̓G���[�g�O�����̎q�Ƃ��ĕč��Ő��܂�A�e����]�X�Ƃ��Ĉ炿�A���Ǔ��{�ɋA��⍂�Z����ɂ͗������ڂ�A�\�͎����Œ�w�܂Ōo�����Ă���Ƒ��ƁB���A�Ƃ��Ă��i�w�͖����ƒ��߂Ă����ނ́A����������w���ł��o�����u��\��|�v�������x�ɋ~���܂��B���̐��x�͉q���w���̌��f�̎Y���������݂̂��A���Ɏ��̐S�����߂��Ă��܂����B
�@
�i���Z���ォ��A�����Ȏ��ɌX�|���ēo�R���n�߂�����ł����̂Ɂj����N�́u�݊w���Ɏ��嗤�ō����o���v����ĉ��Ƃ����w���ʂ��������̂́A�o���ɐ旧�����̃��h���������ꗶ���Ă������A�����m�����q�����͖���N���w�����ɌĂ�ŗ�܂��A���̏�Ŏ������g��200���~�܂Ŏ�n�����Ƃ̂��ƁB�ŋ߂̎t��W�ł͋H�ɂ݂���k�ł͂���܂��B�ނ�ʼnq������̂����������F�肢�����܂��B |
 |
2007�N12��18�� |
|
 |
�@���ڗ͞D�N����u�n�ӖL�a�搶�i���̃��j�[�N�ȍ�i�ƌ����ɂ���āA���z�E�ł͗L���Ȍ��z�Ɓj���}���K���U����Ƃ����w�̑n�ݍ\�z��ډ����i���Ȃ̂ŁA��c����ɉ�������Ă�����c�v�Ƃ����\��������Ă����̂ŁA���CCT�Ŕ��ڌN�������A���H���k�̋@��������܂����B
�@
�l���q���̍��A����ƌ����Γc�͐��A�́w�̂炭��x�ɑ�\�����悤�ɁA���e���\���`�����P���Ȏq�������́g�ǂݕ��h�ł������A���A�Ƃ��ɂ������\�N���̃}���K�͌���A�Q�[���A�A�j���c�Ɨ̈���g�債�A���̕��G�ȓ��e�ƕ\���`���ɂ���Ă�����N��w�ɑ����̈��D�҂����|�p����A������Y�Ɓi����s��K��5,000���~�j�ւƐi�����Ă��܂��B
�@
�w���o�r�W�l�X�x12��3�����̓��W�u�n���E�b�h���{�A�j����ۂށv�ɂ��ƁA���{�̃|�b�v�J���`���[�ł���e��g�}���K��i�h�́A���łɕč��͂��ߐ��E�e���́g�R���e���c�E�r�W�l�X�h�̐���҂���ڋq�܂ł��L���������āg�N�[���E�W���p���h�̖����m�����A���Ƃ���́u�����Ԃ̎��̓��{�̐헪�I�A�o�Y�Ɓv�ɋ[������قǁB�����c�O�ɂ������́A�����̕���u�Z�p�ꗬ�A�����v�ɗ��܂��Ă��܂��B
�@
���̏�m���Ă��m�炸���A�ŋߓ��{�e�n�̑�w�Ń}���K�w���E�w�Ȑݒu�̓������ڗ����Ă��Ă��܂����A�}���K����w�\�z�͐��E�ŏ��߂Ă̂͂��B�����炱���l�́A�n�ӂ���̖��̎����ɂ͍ő�̋��͂��������ł��B���{�̑�w�̌o�ϊ����������𑝂����A�V��w�̑n�݂��u�����X�͗\�z�O�ɑ����A�l�����k�Ȃ������͗v�����Ă���P�[�X�����ŁA��L���܂߂Ėډ�5���ɋy��ł��܂��B���㐔�\�N�̂����ɁA����800�Z�߂������w�̔��������ł��A��100�Z�̑�w���V�݂���Ă����A���ꂪ�l�̐Ȃ��]�I�ϑ��ł��B |
 |
2007�N12��11�� |
| 678 |
�T�ς��S�Q���邾���ł͍ς܂Ȃ� |
|
 |
�@��T�ؗj�A���F�̒琴��N�Ƌv���Ԃ�Ɋ��k����@��܂����B����G���̓C�k�ŁA�����i��F�j��y�����ꏏ�ł���������͍ŏ����琷��オ��A�����2���Ԃ������Ƃ����Ԃɉ߂��������C�����܂��B�b��͏I�n���N���y���l�[���̒҈䋪���ōŋߏo�ł����w�V�c���_�x�i�W�p�Ёj�B���̖{�œ��N�́A�u�l��������ɕ\���ɓ������Ă���̂́A���オ�i�푈�̕��ւƂ��A�匠�ݖ��łȂ����ւƂ��A����j�������X���͂��߂Ă���Ƃ�����@���ł���v�Ƃ��̎��M���@���u�܂������v�ŏq�ׁA�ŏI�͂̍Ō���A��������ł��܂��B
�@
�u���݁A���͂��l���Ă��鐭��́A�C�O�Ɍ����Ă͍����J���A�����I�ɂ͖��O�̌������\�Ȍ��艟�����A�L�������킹�Ȃ�������m�����Ă��܂����Ƃ̂悤�Ɍ�����B�������A���̐�����i�Z���Z�[�V���i���Y���ƃZ���`�����^���Y����g��Ƃ��郁�f�B�A�̐��_�`���͂�O��I�ɓ������邱�Ƃɂ��j���O�𖡕��ɂ��Ēf�s���悤�Ƃ��Ă���悤���B�c�����Ŗl��́A�{���͖��O�̊�]�ɍ��v����悤�Ȏ匠�ݖ��ƕ��a�v�z��ɂ��āA���������ɏ��o���ׂ������ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B����v�ƁB
�@
���N�̗F�l�̏�R�O�Y�N�́A�펞��18�ɂ��Ĉ����̏�������������A�����P�\��ԏサ�ē��ʊ������K���Ƃ��ĊC�R�Ɏu��������܂����B��������N�́A��㖯�剻�Ɍ������ĕ��݂��������{�ɍ��������̋C�z�����܂ꂽ�Ǝ@�m�����A�키�ׂ���w���̐g�ňꎞ�͋��Y�}�֓��}�����Ƃ��`����ꂽ��M�Ƃł����B���60�N�A��R�N����N���l���S���ΏƓI�Ȑl������Ƃ͌����A�c���̌����T�ς��S�Q���邾���ł͍ς܂Ȃ��v���͊��S��v�B�c��̐l���A�l�͍L�����u���������A���\�Ȍ��͂Ɛ키���ӂ�V���ɂ��Ă��܂��B |
 |
2007�N12��4�� |
| 677 |
JapAnglo-Saxon�@capitalism |
|
 |
�@��T���������ꂽ�����h���w�G�R�m�~�X�g�x�ɁA�v���Ԃ�ɓ��{�Ɋւ����^���W�i20�y�[�W�j���f�ڂ���܂����B�\��́uGoing�@hybrid�v�ŁA�ŏI�͂͑肵�āuJapAnglo-Saxon capitalism�v�B�v����ɁA�s�����ȓ��{�̋ߖ�����_����ɓ�����M��T.Standage�́A����g���E��̎����ԃ��[�J�[�h�g���^���ւ�n�C�u���b�h�J�[�u�v���E�X�v�̐����ɂȂ��炦�A���{�̊�Ɓi���o�ρj�̉^�c�������^�Ɖp�Č^�Ƃ̃n�C�u���b�h�ɂȂ��Ă������Z�͍����A��������������ė������������{�����E����Ăѕ]�������\�����������Ă��܂��B
�@
���͑S�����R�ł����A����n�߂ėF�l���p�́u�v���E�X�v�ɏ��A���̏��S�n�̉��K���͂Ƃ������A���̊����ׁ{�R��̒Ⴓ������āA���߂Ċ������Ă��܂����B�����I�ȏ�̗��j�����Ƃ����n�C�u���b�h�J�[�ł����A�e���̎����ԃ��[�J�[�����̎��p�I�J���ɏ��o�����̂́A��80�N��̐Ζ���@�ȍ~�̂��ƁA���̒��Ńg���^���Ǝ��̋Z�p��ςݏd�˂������\�����u�v���E�X�v�͖ډ��̂Ƃ��됢�E�ňꓪ�n�����݂ł����A�g���^�����łȂ��z���_���n�ߍ��Y�e�Ђ̊J���w�͂̐��ʂ����E�ō����]������Ă��܂��B
�@
�ُ�C�ۂƂ���ɔ����ЊQ�����E�I�ƂȂ�ƂƂ��ɁA�����̉����ɑ��Ă悤�₭�e���̎w���w�݂̂���ʏ����܂ł������S�������n�߂����݁A�n�C�u���b�h�J�[�����łȂ��A��C�␅���̉����h�~�A�p���������ƃ��T�C�N���A�N���[���G�l���M�[�A�X�сE�͐�E�C�m�̊��ۑS�c�Ƃ�����������g���Y�Ɓh�̕���œ��{��Ƃ̊��ڗ����܂��B��q�̓��W�����{�̂��̖ʂł̍v���ɑ傫�Ȋ��҂��Ă��܂����A���{�̏����ɑ��T���ĔߊϓI�Ȗl�Ƃ��ẮA���̏��ɓI�p������{�ʂ̊O���l���炶������@���ꂽ�v���ł��B |
 |
2007�N11��27�� |
|
 |
�@����Ƃ̑啔���͓�������̓s�S�ɖ{�Ђ�u���A�܂��A�L����w�̑啔���͎�s��������̍D���n�̏ꏊ�ɃL�����p�X���\���Ă��܂��B�������A�V�l�̗̍p�ɓ������đ���Ƃ͗L����w����D�悵�A�t�ɏA�E�ɍۂ��ėL����w�̊w���͋����đ���Ƃ��u�]���܂��B���{�I���F�̈�ł��B
�@
�l���猩��A����Ƃ̑����͕K���������͓I�ȏA�E��Ƃ��v���܂��A�L����w�̑��Ɛ��̑����͕K��������Ɛl�Ƃ��Ă̓K���̎�����ł�����܂��A�Ȃ������łȂ���Ƃ̑������L����w�������߁A�܂��A�L���łȂ���w�̊w���̑���������Ƃւ̏A�E�����߂܂��B���ʂƂ��ċN�����Ă���l�ޔz���̕s�ύt�́A�B�ꂽ���ƓI���̂͂��B
�@
�������s�����}�X�R�~���܂�����ɋC�Â��Ă��܂��A�u��肠��Ώ��@����v�ŁA���̐�D�́g�j�b�`�E�}�[�P�b�g�h��N�����J������Ɩ����Ɏv���Ă����Ƃ���A������ɂ��̈�l����㗙�i�N���킴�킴�l�̐ԍ�I�t�B�X�ɘA��Ă��Ă��ꂽ�̂ł��B�R�ߋ`�K���A46�B�R�����ɐ��܂�炿�A���Z����傫�ȍ��܂𖡂������L���㗝�X�Ȃǂɋ߂��ƈӗ~�ɔR���Ĉ�Ƃ��N�������̂ł����A���̖ړI�́A�i���炭�����g�̒ɐȌo������ɂ��ẮA�b�܂�ʌo���̎�҂ɑ���j�A�E����э̗p�x�����ƁB���̍˔\�Ɠw�͎͂���̗v���Ɍ����ɍ��v���āA���Ƃ͑听�������߂܂����B
�@
���̒����w����̒B�l�x�͒��l���ł͗�́w�ʐڂ̒B�l�x�i���J���G���j�̔�������悤�ɁA�����{����Ɏ��Ƃ�W�J���Ă������́A���悢��S�𓌋��Ɍ�����悤�ł��B���������A��T�ؗj�[�A���̎��Ɓi��������ЃU���f�B�A�W�����j�n��20���N���ӍՂ֏o�Ȃ��Ċ��t�̉������Ƃ�܂������A���̔M�C�Ɋ�Ƃ̔��͂�Ɋ���������ł��B |
 |
2007�N11��20�� |
|
 |
�@6���Ԃɂ킽�铌�k�ւ̍u���Ɖ�̗��̍ŏI�n�_�͏H�c�B14���ߌ�H�c�s�x�O�̍��ۋ��{��w�Łu�g�b�v�����c�v�A���̖�i���Ɖ��~�̒��j�p�ٍx�O�̎R�����̏h�ɏ���ڂ��Ă̍��k��A�Ƃ��ɒ��Ԃ͒�����Y�w���̂ق����N(�����A���������j�A���쐳�\�Y�i���������j�A�ҕ��g(�H�c���H��c�����_�)�Ɩl��4�l�݂̂ł�������A��c�ł͊����态A���k��ł͘a�C�\�X�A�s���Ȃ��b��Ɖ�b�Ɋ��S�Ɏ���Y��܂����B
�@
�{���w�������Ă��������c�m���̂��˗��ł��̑�w�̑n�ݏ����ψ��ɂȂ����l�́A�ψ����̒����N�ɋ��͂��Ċv�V�I��w�̑n�݂�ڎw���A�J�w����g�b�v����ψ��ɖ���A�˂Ă��܂��B���������������ƂɁA�@���Ƃ͑S�ĉp��A�A�w���͏����őS�����A�B���E�e���̑�w�ƒ�g���A�݊w���ɗ��w�̌��c�Ƃ��������݂͐��Ԃŗ\�z�O�ɍ������ڂ𗁂сA��������{���A���l�A�A�E���藦�c�Ŋi�i�̕]���Ă��܂��B
�@
���x�̓��k�̗��̃n�C���C�g�́A���Ƃ����Ă��Ō�̖�B��ƂŖ��𐬂���4�l�̐l���Ɗ��k�̎����߂����F���[�߂������ƂƂƂ��ɁA���k�̏�ƂȂ����h�̑z����₷��f���炵���������˂Ȃ�܂���B�Â������R�����Ԃ�30�����o�肫�����ꏊ�ɓˑR�o������ʓV�n�A���̖��́u�s�킷��v�B 9�������Ȃ����قƂ͂����A�S�������ꗬ���ٕ��݂̓����E�ݔ��𐮂��Ă����ɁA24���Ԃ���ƗN���o��I�V����̓������B���E���W��H���̍C�������C���e���A�Z���X�A���̓O�ꂵ�����ĂȂ��Ԃ�A���̑��ʂȗ����̎|���c�B
�@
����2���t�W�e���r�́u�U�E�x�X�g�n�E�X�P�Q�R�v�ŁA���ɂ̌��ꉷ��h�ō��ʂɂȂ������Ƃ͓��R�������܂��B�邪�ӂ��A��I���A�����ɖ߂��ēƂ艷��ɐZ����Ȃ���A�l�͎b���s��Y��A���R�Ɠ��k�̎����̈łƑ��Ă��܂����B |
 |
2007�N11��13�� |
| 674 |
�f���炵���`�����E�~�����E�t�� |
|
 |
�@�l���ł��h������I�[�P�X�g���w���҂́A�؍��l�̃`�����E�~�����E�t���B�����m�̂��Ƃ��A�ނ͉��Ċe���̈ꗬ�I�[�P�X�g����I�y�����c�̎w���҂��C���A�܂������̋P���������y�܂���܂����ق��A���̎Љ�v���ɂ�胆�l�X�R����gTHE MAN OF THE YEAR�h�i95�N�j�A�ꍑ���{����͍ō��ʂ̕����M�́w�����x�i96�N�j���Ă�����̐l���ł��B
�@
�̂���l�͂��̗͊��Ƒ@�ׂ������������w���Ԃ�ɖ�������Ă����̂ł����A���N�O�A���R���̒g�������J���I�Ȑl���ɒ��ڐG��Ĉȗ��A��i�ƌh�������[�܂�܂����B�Z�{�̋��S����z�e���i���C���^�[�R���`�l���^���z�e���j�̃��r�[�ŗF�l�ƎG�k�����Ă������A�ނ�����ʂ肩�������̂ŁA�v�킸�����������̂ł����A�����m�炸�̖l�̊�����߂��A�ނ̓j�b�R������ʼn�߂�Ԃ��Ă��ꂽ�̂ł��B
�@
���̃`��������̐�T���j��̃T���g���[�z�[�ł̌����ɍ��킹�A�l�̕č��l�̐e�F���b�N�E�_�C�N���A������u�}�G�X�g���E�`�������͂ލ��e��v��݂��A�l�ƃ��C�t�����҂��Ă���܂����B�������l���Ńe�[�u�����͂ނ����Ƃ����W���ł�������A�l�͍��x�̓`��������Ƃ����Ɋ��k�̎����߂������������łȂ��A�ӋC�������ē���������������܂����B
�@
���������Ƃ��̗����A�ނ́u���j���ɋA������O�ɁA������x�l�Ɖ���Ęb�������v�ƁA�킴�킴���b�N�ɓd�b�A�������Ă����Ƃ̂��ƁB�����ɂ��l�͓��k�ɍu���ɏo�����Ă��܂��Ă��Ďc�O�ɂ��ĉ�͂ł��܂���ł������A�`��������Ƃ͍���K���F��[�܂�Ɗm�M���Ă��܂��B���{�ɂ��������������{�l����������ȏ�A�l�͍��ЂƊW�Ȃ��h���ł���l����F�Ƃ��A���̗F�����ɍ��ƍ��Ƃ̗F�D�W�ɏ����ł��v���������Ə�ɐS�����Ă��܂��B |
 |
2007�N11��7�� |
| 673 |
�����������{�l������c |
|
 |
�@���Ղ�������͐_�X�����A�ǂ��̍��ł������̎���ł��A�l�X�̐��h�̓I�ł��B�������A���̎R�X�̒�����ɂ߂邱�Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��A�����Ȓm���A�o���A�Z�p�c��g�ɂ����l�X���g�o�R�Ɓh�Ƃ��Ė��𐬂����Ȃł��B
�@
�����̓��{�ōł��L���ȓo�R�Ƃ̈�l�͖�����N�ł��傤�B�{�X�g�����܂�̋A�����N�B16�Ń����u�����o���B25�Łu���嗤�ō������E�ŔN���o���L�^�v�B���c�ƎႭ���ċP���������т��c���܂������A�ނ�����ɗL���ɂ����̂́A�G���F���X�g�ɑ͐ς����S�~��������ׂ�����g���|�o�R���h���������A�����Ɉ�V�I�����悵�����Ƃ̂͂��ł��B
�@
���̎��т̌̂ɁA�挎���{�s��ꂽ���N�́u����܁v�I�l�ψ���ł́A���\�l�̌��҂̒����瓯�N�����|�I�Ȏx���āA��N�̖�c�G���N�Ɏ���2��ڂ̎�҂ɓ���B�l�͐�T���ψ����Ƃ��Đ��c�J�̓��N���K�ˁA����̊m�F�����������ƂƂ��ɁA���߂ē��N�Ɗ��k����@��܂����B
�@
�l����w����́u�X�L�[�R�x���v�ɏ������Ă��܂������A������s�풼��̂��ƂƂāA�C�O�����Ȃǖ��܂����B�����������{�A���v�X�̎R�X�ɓo���������x�ł����A�����͍��R�Ɂg�S�~�̎R�h���ł���ȂǂƂ͖��ɂ��v���Ă��܂���ł����B
�@
���N�̌���p�����{�l�o�R�Ƃ́A�����I��j���N�B�25�B����N���������Ȃ������u���嗤�ō������_�f�P�Ɠo���v���u���A���łɎc���͓�ɂ̃��B���\���E�}�b�V�[�t�ƃA�W�A�̃G���F���X�g���̂݁B���������̓��Ɋւ��Ă͌��n�̐��x��g�P�Ɓh�͋�����Ȃ����߁A�ډ�����I�v��𐄐i���B�䂪�F�ߓ������E�V�c�G�Y���N�͂��łɓ��N���x�����Ă��܂����A����l�͐ԍ�̃I�t�B�X�ł�����l�̗F�A���c���N�ɓ��N���Љ�A�V���ȋ��͂����肢��������ł��B |
 |
2007�N10��30�� |
|
 |
�@20����A�����G��Y�������B�ނ͒n���Ȏ��،����Ɋ�Â��Ē������Ă���������Ƙ_���v�V���A�܂��V���R�����@���[�ɔ������g���F���`���[�h�̐�i�����푁�����{�ɓ`�����w���Ƃ��Ė��𐬂��܂������A�l�ɂ́A�ň��̗F�g�G����h�B
�@
40�N�O�A�m���ƕi�i�ƗD�������߂����̏Ί�ɖ������Ĉȗ��A�l�͉��������̐l�ƈꏏ�Ɏd�����������ƔO�肵�Â��܂�������A20�N�㑽����w�n�݂̈˗������A�D�@�����ƁA�����w�����^����ɔނ�K�˂��̂ł��B
�@
�����ނ͐�C��w�̊Ŕ����������݂̂��A�}�X�R�~�ł��劈��̐g�ł������A�l����X�ƒ������\�z�������ƕ�������A�u�N�̍\�z�ɋ������B�A���A�w���Ȃ炨�f�肷��c�v�ƌ����āA���Ƃ��̏�Ŋw�����A�C���������Ă���܂����B
�@
���̏u�ԁA�l�͑�����̐������m�M���܂����B�ʂ����đ�����́A���N�x�̓����{��33�{�Ƃ�����L�^�Ŕ��������݂̂��A���w�E�o�c���ʂőł��o�������X�̊v�V�I�{��ɂ���āA���u��w���v�̐�i���f���v�Ƃ��ċr���𗁂т��̂ł��B
�@
������̑n�����̐����́A���̑唼��ނɕ����Ă��܂��B�m���ɂ��̊Ԗl�͊w���ł������A�ΊO�I�Ɩ��ɒǂ��Â����l�ɑ��āA�w���Ɩ���K�ɍق��A�w���̐l�S�������ɂ܂Ƃ߂��ނ����A�����I�Ȋw���ɑ��Ȃ�Ȃ���������ł��B
�@
�ޔC�𗂔N�ɍT�����H�A�l�͔ނ�S�苭���������āA���Ɏ����w���A�C���������ĖႢ�܂����B���A���̒���A�a�����ˑR�ނ��P���܂����B�����āA�ނ��h�����鑽���̐l�X�̊肢�����A�a�q�v�l�̗܂��܂������̍b����Ȃ��A�\���N�̓��a�����̌�A�ނ͐��ɋA��ʐl�ƂȂ����̂ł��B25���̍��ʎ��ł̒����ŁA�l�͍Ō�Ɂu�U����A�c������U����v�̈�����A���̐��̏G����Ɏb���̕ʂ�������܂����B |
 |
2007�N10��23�� |
|
 |
�@�h�������y�̕����i��F�j���㋞�����ۂɁg���W�d�b�h������ƁA�l�͗]���̂��Ƃ��Ȃ������莞�Ԃ������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B��T�Ηj�̓z�e���I�[�N���Œ��H��H�ׂȂ���u21���I�̉�v�i��������������Ƃ������j�̑ō��킹������͂��ł����B���A�O���̗[���ˑR�ٗ�ً̋}�d�b�B
�@
�u�m�_�����A���Ӊ��Ƃ��Ȃ�ˁB�i�c���j�^�I�q����ƍ����i�M�j�N�ƂœC�k����͂����������A�ޏ��ɋ}�p���ł�����ŗ\���ς��A�j3�l�ň���������Ȃ����c�v�B�Ƃ����킯�ŁA�l���������̖�̗\���ς��A�S��点�ĐV���́u�ǂ̉Ɓv�i�g�啪�ӂ��h�̐��X�j�ɏo�����čs���܂����B
�@
�c�����N���u21���I�̉�v�̉���ł��邱�Ƃ���A���ނقǂɐ����قǂɘb�͂ǂ����Ă����̉���ł����R�i�O�Y�j�N�∢�v�i�I�j�N�̒Ǒz�ɂȂ�܂����B�����N�͋H�L�Ȑ��_�I��������ێ�������R�N��l���̎t�Ƌ��A�t�̎���͑������ŒǓ����i�ŐV���́A�������l���Ƌ��҂́w��R�O�Y�@���̗��x�A�u�k�Ёj���o�ł��Ă��܂��B���̍����N�ɑ�����l�́A����Ȃ��Ƃ��������C�����܂��B�u�l�����ɂ͏�R�N�̗��z����������g���������B���A��簂ȗ��z����������ɂ́A��R�N�͗]��ɂ����_�I�ɏ����߂�����Ȃ��́c�v�ƁB
�@
�����S�n�ŋA���ƁA�V���Ђ��爢�v�N�̍Ō�̒���w���炩�ȉ}���x�������Ă��Ă��܂����B���l�̂��z���Ɋ��ӂ�������ɂƂ��ăy�[�W���߂���ƁA�u���ŗ����Ő^�������Ō��g�I�Ł@���炸�@�l�Ԃɂ͂ǂ�������ˁv�Ƃ����������ڂɔ�э���ł��܂����B�u�ԁA�l�͂ӂƎv�����̂ł��B
�@
�u�ނ���R�N�ɗ�炸�����Ȑ��_�̎����傾�������A��R�N���ь��������l�Ԃ̏��Ƃ܂ł������Ĕے肵�Ȃ��g���ρh�����������炱���A���̑��ʂȍ�i�͐��܂ꂽ�c�v�ƁB |
 |
2007�N10��17�� |
| 670 |
�����̗F���h�点�Ă��ꂽ���̍� |
|
 |
�@�O�N���̕č��̐e�F�A�G�b�Y�iE�E���H�[�Q���E�O�n�[���@�[�h�勳���j���������ł��B�Z�����Z�ȑ؍ݓ����̍��Ԃɐ�T�y�j���H�����ɂ��A�v���Ԃ�̊��k�Ɏ���Y��܂����B
�@
�ނƓ����Ŏn�߂ĉ�����̂�1959�N�ł������A���N�Ėl��MIT�ɒ��C���đ��X�A�{�X�g���̖l�̉Ƃɂ���Ă������铌�勳����l�̎Ԃɏ悹�ăC�F�[����w�܂ő��������A����ő҂��Ă����̂��ށB���̗��N�ނ��n�[���@�[�h�ֈڂ����̂��_�@�ƂȂ�A�ȗ��j�b�N�l�[���ŌĂэ������ƂȂ����̂ł��B
�@
�������Ԃ����̊Ԃł͔�r�I�n���ȑ��݂������G�b�Y����R�P�����̂́A�Y�������79�N�A��́w�W���p���E�A�Y�ENo.1�x�̏o�ŁB���x�����ɂ���Čo�ϑ卑�ƂȂ����킪�����A���ő�̍���Ƃ�����ēx�̐Ζ���@�������O�̋Z�p�͂ƒc���͂ɂ���ĉ��Ƃ��������AG7�T�~�b�g��c�𓌋��ŏ��̃z�X�g���Ƃ��ĊJ�����N�B�����ɂ��̃W���f�B�E�I���O�́u�������āv�̂���т₩�ȃ����f�B�[������Ă������̍��c�B
�@
�薼���̂��̂����{�l�̐S���������������肩�A�uG7�o�Ȏ҂̕K�Ǐ��v�ȂǂƂ܂Ō��`����A�M�����x�X�g�Z���[�ƂȂ����͓̂��R�ł����A�����̓��{�͐��E���ڂ̓I�����������ɁA�e���ł��|����ނ̖��͍����L����A���E����́g���{�̌�蕔�h�Ƃ��Ĉ���������ƂȂ�܂����B
�@
���̕č��ł��\�������̃x�X�g�Z���[�ƂȂ����{���ł������A�����G�݂��玩���Ԃ܂ł̐��܂����A�����{���i�̔×��ɒ��ʂ��Ă����č��l�̔����͕��G�ł����B�Ƃ��ɁA��@���ƕΌ��̋������������E�w���҂�w�҂����̔ᔻ�┽���́A���ړI�ɂ��ԐړI�ɂ��ނ𑊓��Y�܂����ɈႢ����܂���B
�@
�����ɔ䂵���炩�ɐ��ނ������Ɏv������{�̖������A�ނ����ς�炸�g�����y�ϓI�Ɍ�����̂��A�Y����܂���B |
 |
2007�N10��10�� |
| 669 |
�F�̗F��F�Ƃ��Ă������߂� |
|
 |
�@�����N���ɓǂ܂��Ǝv�킸�ɓ��L�������l�͂��Ȃ��ł��傤�B�Í������̗L���l�̓��L�̑����́A�i��ɕҏW�o�ł���āj���j�I�����╶�w��i�Ƃ��č����]�����Ă��܂����B����ł��̂̐l�́A�����̓��L�����l�ɓǂ܂�邱�Ƃɂ��߂炢���������悤�ł����A����l�ƂȂ�ƁA�����⎄�������J���邱�Ƃɂނ���ϋɓI�Ӗ��������Ă���A���ꂪ�g�����j�h�Ƃ��g�u���O�h�̃u�[���̑f�n�ƂȂ����͂��ł��B
�@
�Ƃ���ŁA20�]�N�Â��Ă���l��Rapport�́u���L�̑���́g�T�L�h���H�v�Ɩ����A�����́uyes��no�v�B�l���L�^�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�e�����F�l�E�m�l�����̎莆�Ƃ��ď����Ă���Ƃ����_��no�ł����A�����ł͂������ɏ����ޗ��ɋ�����������邪�̂ɖ��T�Ƃ����_��yes�Ȃ̂ł��B���������A�W�b�h�ɂ��Ă��ו��ɂ��Ă��A���L��ǂނƁA�����L���قǂ̂��Ƃ��Ȃ��������͑��������悤�ŁA�ӊO�ł��B
�@
Rapport�͖l���J���������f�B�A�B���N�ɂȂ��Č�F�͈͂��L����߂��A��F��g�߂Â��鎞�Ԃ̐�ΓI�s����ɁA�u�����̍ŐV�ő�̊S���͉��ŁA�Ȃ��������Ȃ����S���Ă��邩�c�v�T����I�ɏ�������Â��Ă����킯�ł��B����Ƃ�����̑�ȖړI�́A�ŋߒm�荇�����f���炵���l���ɂ��ĕ邱�ƁB��]�����A�l�̗F�l�����ɂ����̐V�����F�l���Љ�����Ƃ������߂����邩��ł��B
�@
��T�͖l�̃I�t�B�X�ŁA�ߓ������N����o�R�Ƃ̌I��j���N�i���E�ܑ嗤�̍ō����P�Ɠo�����A���Ɠ�嗤��ڎw�������������{�N�j���A�܂��u�C�^���A���C���̉�v�ŁA�p�����N�i���C�^���A��g�j����_���I�E�|�j�b�X�B�N�i�I�y�����o�ƂƂ��ėL�]�ȃC�^���A�l�j���Љ��܂����B�F�l���������N�Ƃ̌�F��[�߂Ă������Ƃ��A�l�̐��b��ł��B |
 |
2007�N10��3�� |
| 668 |
�L�������@�X�͂����^���� |
|
 |
�@��㐶�܂�́A�Ԍ`�Y�Ƃ̈�͖��ԃe���r�����B�u���̋����ɍł��v�������l���́H�v�Ɩ����A���҂Ȃ班�Ȃ��Ƃ��g�c�G�Y�Ə��J����̖��͋�����ł��傤�B�ŁA�g�c���́u���݂̓d�ʂ̎�����̑n�Ǝҁv�ƌ����ΒN�����[�����܂����A���J���͂ƂȂ�ƁA�����͂����ȒP�ł͂���܂���B
�@
��O��㖈���V���̖����̈�L�҂��������J���́A�I��ƂƂ��ɁA�ނ̎��ƃZ���X����i���y�̖�������ŁA�������̃}�X�R�~�̐��E�œ��ق̍˔\�𑶕��ɔ������܂������A���̔ނ�40�̓�������Ŗ����V���ЂɓˑR�ʂ�������A���u�Ƒ��v�莩���̖������R�Ɏ��Ɖ����ׂ��A53�N�����ɇ����W�I�e���r�Z���^�[�Ȃ��Ђ�ݗ����܂����B
�@
���Ƃ��̔N�A�킪�F���c���N�͑�w���Ƃɓ�����A�}�X�R�~�ƊE�̂��Ƃ����J���̂��Ƃ��m�炸�ɓ��Ђ������̂ł��B���̐V���Ј��̖ʐڂɎ��瓖���������J�ꖱ�̂��ዾ�ɂ��Ȃ����Ђ��ʂ��������N�ł������A���Ќ�͏��J���̐l���ɍ����قꍞ�݁A���̕G���ŒZ���Ԃ̂����Ɏd���̐i�ߕ��݂̂��l���ςɂ܂ő傫�Ȋ������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
60�N�Ɏ31�œƗ����Č��݂̃r�f�I�v�����[�V�����Ђ�ݗ��������N�́A�Ȍ㔼���I�Ԏ�Ƃ��Ė��ԃe���r�����E�𒆐S�Ɏ��Ƃ��g�債�Ă��܂����B�O�m�̂��Ƃ����̊ԃe���r�ԑg�̒ᑭ�����}���ɐi�s���Ă������ŁA�v���S���t�w�}�X�^�[�Y�x�̐����p�A�w���[�c�A���g�x��7���ԓ��ԕ����A���������V���[�Y�w���E��Y�x�c�ȂǂŒᑭ���̔g�Ɍ����ɍR���Â����Ƃ���ɁA���c�N�̐^����������܂��B
�@
��T���j�A�ߊ��̈ꏑ�����ɓ��c�N�ƑΒk���s�����ہA�l�͂��̕W����w�L�������@�X�͂����^�����x�ɂ�����A�ƍl���܂����B���̗��R��m�肽����A���������y���݂Ɂc�B |
 |
2007�N9��26�� |
|
 |
�@���Ƃ������R�c�B�e���������u�����}�̐V���فv��匩�o���ŕ����A�̕�����Łw���n���䂭�E���u�сx���Ϗ܂��܂����B���C�t�Ƌ��Ɉ�㗙�i�����v�Ȃ��炨�������Ă����G�R�Ց�̕��ꒋ�̕��̍ŏ��̏o�����������̂ł��B
�@
�\���܂ł��Ȃ��i�n�ɑ��Y�̑�\�������Ƃ������̂����ɁA��{���n�Ɣނ̎v�z�ƍs���Ɍ���I�e����^�������C�M�Ɠ�l�̐l����������Ŏ�X�ɑf���炵���������邱�Ƃ͗\�z���Ă��܂������A���������J���Ă���͂���Ȃ��Ƃ͈�ؖY��A�v���Ԃ�Ɏŋ��̖ʔ����Ɉ������܂�܂����B
�@
����A���䖲���Ŋό����Ă��邤���ɁA�l�͎v���������J���̏�T�u�ƐS���ɗN���o�Ă���̂��������ł͂���܂��c�B�Ƃ��ɂ��̎ŋ��̃N���C�}�b�N�X�Ƃ��������O���u���C�M���~�v�ŁA�C�M�����n��{�C�s�������������ʂł́A�����̓��{�̊�@�I�Ɏv�����A�����܂����B
�@
�O�̓��̃e���r�ł������̐V���ł��A���c���́u�����}�͈�ɂȂ�˂c�v�Ƃ�����ɋ������Ă��܂����B���鏬�͂��̊�Łu�N�����قɂȂ낤�ƁA�����}��ǂ����ށc�v�Ɛ������Ă݂��܂����B�Ƃ��ɓ}�����č��Ȃ��A������{�̎w���҂ɂ́A����������Ă����@�����S���������܂���B
�@
���Ȃ��Ƃ��ŋ��Ƃ͂����A�C�M���琢�E�n�}���������u�c�˂Ȃǂɂ�������Ă��Ắv�Ƃ����Ȃ߂�ꂽ���n�́A�y���Q�m�𖼏�����Ȃ�p���A�Ђ�����|�����ɂ͂�����Ȃ̖��n���ɖ|�R�Ɩڊo�߂܂��B�������t�ɔN���̊C�M�́A�u�c���{�Ȃǂɂ�����炸�v�Ɛ������n�̌��ɁA�i���J���R�̂��ƂƂ��Ă����Ȃ̑��傳��|�R�ƌ��܂��B�l���I
�@
���͎㏬�������Ƃ͂����A�����̓��{�ɐl���͂��܂����B���E�L���̌o�ϑ卑�Ƃ͂����A���̓��{�ɂ͐l�������܂���B |
 |
2007�N9��18�� |
|
 |
�@�u�c�c��������a�C�ЂƂ��Ȃ��܂܁A���C��80���}�����B�җ���߂������A�N�̗F�������Ő��܂�Ă͂��߂Đl�ԃh�b�N���肵���������ʂ��I�[��A���������A�N�͌���������Ȃ����B�w���Ȃ����̂���Ȃ��B�S�Ă�DNA�̂������B�c��̂���֍s���Č��������Ă��Ȃ����c�x���āv�B
�@
�G���wJACT�x�̍ŐV���ł̈����a�F�N�Ƃ̑Βk�`���̖l�̌��ł��B�����N�͐l���m�铌���w���ŔN�������̋L�^�z�[���_�[�B�Ⴍ���ĐS���O�Ȉ��ڎw���Ȃ����㓌��ɐ�[��Î{�݃Z���^�[���J�݂����ƂƂ��ɗՏ���̓���f�O���A�ފ��܂œ��{�̍��x��ËZ�p�̊J���Ɏw���I�������ʂ����Ă�������̖����������̖��������ŁA�l��40�N���̐e�F�B
�@
���̓��N���ފ���ُ�ȔM�ӂŎ��g�̂́A�g���m��w�h�Ƃ��̑��̍��X�̓`����ÂƂ̓����B���ď����͂�������ȍ~�̓��{�ł���Â̎嗬���߂����m��w�́A���Â̑O��Ƃ��āA���a�̌����̊w���I�����ɏd�_��u���܂��B����A�����̍��́g�`����Áh�i�킪���Ȃ�A�I�E���A�����A���́c�j�͕a�C�̗��_�I�𖾂��́A�����o���Ɋ�Â��L���Ȏ��Âɏd�_��u���čL�������̐M���Ă��܂����B
�@
���m��w�̍őO���ɂ��������ɁA�����N�́u�w���ɕ�߂��Đ�啪���̐r���������m��w�ł́A���͂�l�ԑS�̂�f�邱�Ƃ͕s�\�c�v�Ƃ�����@���ɋ���A�e����̓��u����������98�N�u��ցE����E�`����ØA����c�iJACT�j�A00�N�ɂ́u������Êw��v(JIM)��ݗ����A�ډ����ꂼ��̗������A��̗v�E�������Ĕ��ʘZ�]�̊������ł��B
�@
������Â͌X�̊��҂̂��߂݂̂��A������\�h�����N��w������܂��邱�Ƃɂ��A��Ô��Ƃ��������̍��ƓI���̉����̂��߂ɂ��A����̑�Ƃ��Ċ��҂���܂��B |
 |
2007�N9��11�� |
|
 |
�@�V�w����9���A�����V�N�ȋC�����ŋ��d�ցc�A�Ƃ������Ƃ̂Ȃ��H���̕�����Ȃ��B�����ł��B�Љ�l�Ƃ��ĐS�Ȃ炸����w�̐��E�ɓ������l���A���̒��Ŕ����I���߂������̂́A���t�Ƃ����E�ƂɂЂǂ������b��������Â�������ł��B����͋��炭�A���{�̑�w�����Ƃ��Ă͋H�L�ȗ�ł��傤�B
�@
���{�ő�w�����ƂȂ�l�Ԃ̑啔���͌����Ҏu�]�ŁA���ʂƂ��Ċw�҈ӎ����l�����Ȃ��قNj����A���ꂪ�Ђ����i�g�����h�𗝗R�Ɂj����������ɂ��낻���ɂ��Ă������́A���Ɛ��Ȃ�l���܂ߒN�ł��o�������͂��ł��B�v����ɁA�w����m�I�ɖ����ł���悤�Ȏ��Ƃ��ł��Ȃ���A�l���ς̌`���ɉe����^������悤�Ȑl�i���������A�������낭�Ȍ������т������Ƃ����̂��A���{�̑�w�����̕��ϑ��Ȃ̂ł��B
�@
�S���E�̑�w�Ƃ̔�r�Ȃ������ł����A�l�Ɋւ��ẮA�����I�O��2�N�ԍݐЂ����}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�iMIT�j���v�������ׂ�A�����E���痼�ʂœ��{�̈ꗬ��w�Ȃ������ɂ��y�т܂���BMIT�͓����������N�Ԏ����̉ߔ������������ł���A�m�[�x����܋����͊e�w���ɂ���i���݂�60����́A�����{�̎�ґ�����6�{��j�B���Ɨ������͑S�̂�15���قǂł����A����ւ̗͂̓�����͓��̉�����قǂŁA�m�[�x����܋����ł��A�����ł͎��ɔM�S�ȋ����Ȃ̂ł��B
�@
���{�ł́A��w�̑������g����h�Ƃ������̂�S���y�����Ȃ���A�g�ō��w�{�h�Ƃ��Ă̎Љ�I�n�ʂ�ێ����Ă��܂����B���̋����������ւ̓{�肱���A��w�l�Ƃ��Ėl���g��w���v�h��藧�Ă������͂ł��B���T�̖����V���w�G�R�m�~�X�g�x�����u�ⓚ�L�p�v�Ŗl�����グ�܂������A������ނ��ċv�����l���ˑR�Ƃ��āu��w���v�̎��H�ҁv�ł��邱�ƁA���̂��Ǝ��̂��A���{�̑�w���v�̕s�т���Ă��܂��B |
 |
2007�N9��4�� |
|
 |
�@�Љ�l�ɂȂ��Ă��炻�ꂱ�����߂āA�l�͂���8����t���A�i�����m�̂��Ƃ��ARapport�܂ŋx�M�錾���āj���R�C���ɉ߂����܂����B���̊ԁA�ׂɃu���u�����ĕ�炵���킯�łȂ��A�I�t�B�X�ł͗��܂��Ă����d�������X�ɏ������A�v������Ȃ������F�l���Ăяo���ċ��������߁A�傢�ɓǏ������A���͂������A�Ƒ��Ƃ̗����y���݂܂�������A��O�҂ɂ́A�����̉Ă���X�Ђ����猳�C�ɁA�Z�����߂����V�l�Ɍ������ɈႢ����܂���B
�@
�����l�͂��̈ꃖ���A�T�ԃX�P�W���[�������炸�A�C�̌����܂܂ɓ��X�𑗂�܂����B���̐��������т������ʂƂ��āA���@�J���X�Ɠ��{�̐��l�́g�ċx�݁h�Ƃ̖{���I�Ⴂ���A�P�Ɋ��Ԃ̒��������łȂ����Ƃ��A�����ŗ������܂����B�܂�A�v����\�z�ƌĂ��m�I�w�͂̌��ʂ����߂邽�߂ɂ͂������̂��ƁA�Ƒ���F�l�Ƃ̈���M����[�߁A�ێ�����Ƃ�������I�[���̂��߂ɂ��A�X�P�W���[���ɒǂ��܂����鑽�Z���قǒ��ӂ��ׂ����̂͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��A��80�ɂ��Ă���ƌ�����̂ł��B
�@
�T�^�I�Ȑ��ʂƌ����A��h�C�c�l���z�ƂƂ̗F��̐[�܂�B���{�̌Ö��Ƃ̔��ƍ\���ɖ������A�킴�킴�������ĐV���̎R���ɏZ�݁A���c�ɘV���������_�ƂȂǂ�������ẮA�����ȃf�U�C���Z���X�ʼn��K�ȏZ�܂��ւƕϐg�����Â��Ă���J�[���E�x���N�X�B����7���V���ŊJ�Â��ꂽ�����ɌG����N�ƈꏏ�ɍu�t�Ƃ��ď����ꂽ���iRapport-661�j�A�ނɋ��R�������čD�����������̂ŁA�i8���㋞����Ƃ����ނɁj�u�����Ȃ牽���ł��c�v�ƌ��������Ƃ����ŁA�ނ�2�T�����Đԍ�̖l�̃I�t�B�X�ɗ��܂����B�l�͎��Ԃɔ����邱�ƂȂ��A�ނƎv����������ׂ�A�����ނ��킵�A�H�������ɂ��ĈӋC���������̂ł��B�����A�g8���̎��R�h�����������Ȃ�A�l�����́A�������h���������������̒��Ƃ��Ĉꐶ���I���Ă����ɈႢ�Ȃ��ł��傤�B |
 |
2007�N8��1�� |
|
 |
�@���̈�T�Ԃ́A���{�����Q�@�I��F�A�I���O�}�X�R�~�͂������Ĉ��{�̎�������Â��A���ʂ͂����m�̂��Ƃ��A�����}�̊��SKO�I�@�����s�v�c�Ȃ��ƂɁA�I����}�X�R�~�͖���}�́g�����h���قƂ�Ǐ̂��܂��A���{�̑��X�́g�����錾�h���������ᔻ���Ȃ�����A������t�̏o����M��ɑҖ]���邱�Ƃ��Ȃ��ł͂���܂��c�B
�@
���{�l�̑����͂��̎������͂�����Ƃ͔F�����Ă͂��Ȃ��Ȃ���A���ƂȂ����̂��Ƃ������Ƃ��Ă͂���͂��ł��B��̓I�Ɍ����A�u���̍ۈ��{�̓m�[�B�������A�����}�ɂ͎Ƃ��Ċ��҂ł���l�ނ͐△�B�ł́i���ɐ�����オ�������Ƃ��āj����̓m�[�B�������A����}�ɂ��Ƃ��Ċ��҂ł���l�ނ͐△�c�v�B�����ł��B���ƂɂƂ��čō����͂ł��鍑���ɂ����閣�͓I�w���҂̌���I�����A���₻�̑O�Ɂi�����K�R�Ȃ炵�߂��j����c���̐l�ԂƂ��Ă̎��̕��ϓI�ቺ�����A�����̓��{�̔��犦�������ł��B
�@
�c�ȂǂƊS�Q���鎩�������������Ɣ��Ȃ��Ȃ���A�ӂƍ��͖S���D���ߓc�_����v���o���Ă��܂��B�ԍ�̂Ƃ������Ŕނƌ���g�݂Ȃ���u�����牽�܂Ő^���Èł�c�v�Ɖ̂����̂́A����30�N���̂̂��ƁB������q�Œ����Z�Ȑg�ł���Ȃ���A���N��F�����̈⍜��T���ɓ���ɏo�����Ă����ނ́A�u�c�D�̒�����E���o�����⍜���A��������Ȃ����Y��Ȑ��Ő��߂āc�v�ƌ����Ȃ���A�Ƃ߂ǂ��Ȃ��܂𗬂��̂ł����B�������̐l�����Ɋւ��ẮA���̂悤�ȐS���������G�s�\�[�h�����L�����S���������Ƃ��珟��ɐ��@����ɁA���͓I�w���҂̌����́A��O����ʂ��ĕς��Ȃ����{���̔߂����h���I�����Ȃ̂ł��傤���B
�i�ċG�x�ɂ̂��߁ARapport�̎��M��8����t�x�܂��Ă��������܂��j |
 |
2007�N7��24�� |
|
 |
�@19���鎞���ʐM�z�[���ɂĊJ�Ấu�������t�H�[�����v�ŁA�`���̎�Î҈��A�B���̍Â��́A�������Y�N���i���j���{�����������������ɏA�C����6�N�O�ɓ��N�̔��ӂŎn�߂�ꂽ���̂ŁA�K�����N���œK�̃e�[�}�ƃQ�X�g��I�сA���炪�R�[�f�B�l�[�g���ĔN1��s���Ă������̂ŁA���N�̃e�[�}�́u���E�V�����Ɠ��{�̗����ʒu�\ ���[���b�p�̍s�����Ɋw�ԁv�A�Q�X�g�͖ؑ��ɗʁi�����V���O���[���b�p���ǒ��j�A�����A��i�����w�@�@�w�����w�����ȋ����j�����ł����B
�@
���C���N�̍����ƃC�X�������Ƃ̑䓪�A�u�b�V�������̗����ƂƂ��ɓ��������č���Ɏ�`�̏I���A��������i�卑�o�ς̋}�������������������A�G�l���M�[�卑���V�A�̏o���ɂ��V���ȍ��ۓI�ْ��A�}�l�[�Q�[�����������{��`�̏ے��Ƃ��Ẵz�b�g�}�l�[�̖z���c�Ɛ��E�̑S�Ă̍��������ꏭ�Ȃ���l�X�ȓ�ǂɓ��ʂ��A�܂��w���҂����̑ŊJ�\�͂����Ă��钆�ŁA�gEU�h�Ƃ����l�ދ�O�̑厖�Ƃ̍�������������Đ����ɓ������郈�[���b�p��v�����̍s�����́A�����������ɂ����Ċm���Ɉ�i�ƒ��ڂ𗁂тĂ���悤�ł��B�����Ă݂�ΐ�����Ɗ����镛��̌��ʂ��A�o�Ȏ҂͗\�z�O�ŁA���z�[�������ȂƂȂ鐷���ł����B
�@
�u���g���h�ʼne�𔖂߂Ȃ���A���Y��`�̕����͐����ʂł��o�ϖʂł��}���ɍ��ۓI���݊��������߂Ă����c�v�i�����j�A�u�����`����Ƃ��Ă��A�P��ł��������܂����č��^�ƈ���đ��l�ȉ��l�ς̋�����e�F���Ȃ�������I�蒅�x�͍����c�v�i�����j�A�u�g���h�Ɓg���h�̒��ԂɎs���̎Љ�Q���ɂ���ĐV�����g���h�̊����̈��傫���L������c�v�i�ؑ��j���[���b�p�́A������̍s���������ɖ͍�������{�ɂƂ��āA�����̎�����^���Ă��ꂻ���ł��B |
 |
2007�N7��18�� |
|
 |
�@��T���͓�l�̋��F�����ɂ��܂������A���͓����T�Ɋ�����A������l�̋��F�Ƃ̖Y���o�������܂����B
�@
���j�ߑO�A�������̌���l�N�����Z�ȓ����������Ėl�̐ԍ�I�t�B�X�ɗ��K�B���N�͂܂�55�̎Ⴓ�ł����A�c��@�w���𑲋ƒ���n�āA�X�^���t�H�[�h��w�̌o�c�w��w�@�A���H�w����w�@�I����A80�N��͂��߂���V���R���o���[�����_�Ƃ��ăx���`���[�E�L���s�^���X�g�Ƃ��Ċ����𐬂�����ށB���̋P���������тɂ��A�Ђ⍑�A��č����{�̗v�E�A�Ђ�킪���̐��{�ψ�������ȎQ�^�Ȃǂ������A���ꂱ�����E���҂ɂ������ʘZ�]�̊������̐g�ł��B
�@
�����͓��N���͂ݓ�l�̗F�l���������H���k�B�b��͐�瓯�N�̋ߒ��w21���I�̍��x�_�x�i���}�Ёj�B�N�����V���R���o���[��m�铯�N�́A�����I�����̃l�b�g�o�u���̕����G�������̔j�]���ے����銔������`���č��̎Y�Ɗ�Ղ�Z�����������݂̂���ƌo�c�҂̃����������r�p�������ƒf������ŁA�V�����|�X�g�E�R���s���[�^�Y�Ƃ̓W�J���\�Ȃ炵�߂�Z�p�J���̒S����ƂȂ邱�Ƃɂ���āA���{���Ăѐ��E�̋r���𗁂т邱�ƂɔM�����҂������Ă��܂��B
�@
�y�j���A���z�Ƃ̌G����N�ƐV�����ʼnz�㓒��ցB�u��n�̌|�p�Ձv�J�Òn�̌��������@������A�\�����s�Łu�ق��ق����J��10���N�L�O���Ɓv�Ƃ��Ă̌��J���_�B�G�N�͓��n�Ƀ��j�[�N�ȍ�i���c���Ă���A�l�͂����m�̂��Ƃ�04�N�ȗ�����V�����̋��L�ɔ����ق��ق����̐Ԏ��]���́i���n�݂̂��V�����S�̂ɋy�ڂ��j�댯���Ɍx����炵�Â��Ă����l���ł�����A���͖����B��Ǔ����̕S�_��苇�n��E�����̓I�헪���s�ӌ������A�W�҂��ٖ��ȘA�g��ۂ��Ă��̎��{�ɑS�͓������ׂ����ƔM���i���܂����B |
 |
2007�N7��11�� |
|
 |
�@�g���X���D���h�Ɛ������l���Ƃ͑ΏƓI�ɁA�l�̂悤�ɏ�Ɋ���̐l���ڕW�������A���̒B���ɐ����b���������g�ɂ́A��T�ԂƂ������̂́A���̂����Ɂg���I�Ȏ��ԒP�ʁh�Ƃ��ĐU��Ԃ�܂��B�����炱���A��������Rapport�Ƃ������́g�T�L�g�������Â�����킯�ŁA�g���L�h�ƂȂ�ƁA�������̖l������グ�̓������܂��͕̂K��B�Í������̗L���l�̓��L��ǂނƁA�܂�Ƃ��L�������������������Ă���A�N�����Ǝv�킸�ق����ނ��̂ł��B
�@
���āA�l�̂��̈�T�Ԃ̎��́g���F�h�B9�����ە�����قŏ��ыK�ЌN�i�c����w���_�����j�̐V���o�ŋL�O�����܂����B���N�͍������50�N�O�A�l��MIT�Ŏd�������Ă������Ƀn�[���@�[�h�̃r�W�l�X�E�X�N�[���ɗ��Ă��Ēm�����Ĉȗ��̋��m�̒��ł��B�O�X���痊�܂�Ă����X�s�[�`�ʼn���b�������ƍl���Ȃ���o�Ȃ����̂ł����c�B
�@
�`�����N�l�̈�l�Ƃ��āi�Ԉ֎q�ɏ���Č��ꂽ�j�����������A�̒��ŁA�u�c�i�č����w����j�A���������̎Ⴋ���т���́A�L�\�ȏ�ɉp�ꂪ���Q�Ȃ��߁A�����̊Ԃł͂Ђǂ��]�������������c�v�ƈ���������̂ŁA������Ėl�́A�i�c��W�҂������̂��\���ӎ����āj�u�c�g�o��Y�͑ł����h�̓��{�ŁA�Ƃ��ɑ唼�����ɔY�ޑ�w�����̐��E�ł́A�L�\�Ȑl�ނ͂Ƃ��ɂ����߂ɉ�B���A�������̉�������̘b���ƁA�w�c����A���O�����I�x�Ƃ�������c�B���x���܂��Ȃ�A���{�͐^�����B��͂�C�^���A���ˁc�v�Ɣ����B�Q��҂��甏�芅�т��A�ӋC�g�X�I
�@
�v���A������Ƃ̌�F�͉@�����ォ�炷�ł�60�N�ȏ�A���̔ނ���i�܂����C�����Ȗl�ɂƁj��Ă����^��w�̍Đ��v���W�F�N�g�ɁA�l�͍��ُ�Ȉӗ~��R�₵�Ă��܂��B |
 |
2007�N7��3�� |
|
 |
�@�l�͂悭�u�I��œ��{�ɐ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��̂Ɂc�v�Ƃ����v���ɋ���܂��B���{�l�ł��邱�Ƃ̍K���A��сA�ւ�c���͐S�ꂵ���A�p���������A�T�������c���ӎ��������Ȃ̂́A�O�҂��A�s�K�ȋ����ɂ��鍑���Ɏv����y���đ��ΓI�Ɍb�܂ꂽ���{�l�̓���R�Ɗ�����悤�Ȏ��ł���̂ɑ��A��҂́A�߂��Ȃ��O���l���S�������{�l�ɂ���ĂЂǂ��ڂɉ�킳�ꂽ���Ƃ�m��x�ɒɐɊ����邩��ł��B
�@
��T�͈���{�l�ł���l�̐S���Â������j���[�X���������܂����B��͗�̏]�R�Ԉ��w���c�Ă��č����@�O���ψ���ʼn����ꂽ���Ƃł��B���̌��c�Ă̂������ɂ͑����ɐ����I�Ό������邱�Ƃ͊m���ł��傤���A�]�R�Ԉ��w�͔��t��E�ƂƂ��鏗���ł������Ƃ��A���{�R�����{�͈Ԉ��w�������ɔF�߂Ă��Ȃ������ȂǂƂ����咣�́A���ɖl�ɂ͋�a�ȋ��قɎv���܂��B��O�E�풆�̎���ُ̈�ȓ��{�l����ѓ��{�Љ��z�N����ƁA�u�����I�ɏ]�R�Ԉ��w�ɂ�����ꂽ�����l�����͂��Ȃ������v�Ƃ́A�l�ɂ͂ƂĂ��M�����܂���B
�@
����́A�p�ꋳ�t�Ƃ��ė������������E���ꂽ�p���l�v�Ȃ̃j���[�X�ł��B���̗�E�l���N�����Ă��炷�ł�3�����B�x�@�̌����ȑ{���ɂ��ւ�炸�A�E�l����ł��鎩���{�����ɒǂ��ē��������e�^�҂͂܂����Ƃ��Ďp���������܂܂ł��B�ēx�����������̘V�v�Ȃ��L�҉�̐ȂŎv�킸�܂�@�����p���e���r��ʂŌ������A�������g�̖l���䖝�ł����ɖႢ�������܂����B�p���ɂ����{�ɂ������͂���Ȏ����͓��풃�ю��ŁA��Q�҂̐e���̔߂��݂͓������Ƃ͂����A���������傫�Ȗ�������Ă���Ă����O���̎Ⴂ���������{�ő��������ߌ��ɁA���{�l�̈�l�Ƃ��Ėl�͔ޏ��ɂ��ޏ��̂����e�ɂ���X�ȓ���ƐӔC�������Ă��܂��̂ł��B |
 |