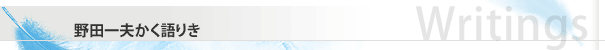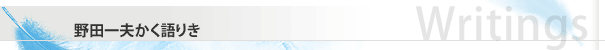大学教授でありながら中年期の大部分を日本の大学に社会的距離を置いた私に、還暦近くなって急に今度は大学の方が近づいてきた。その背景は、「時の運」とでもいうか、八〇年代の半ば頃から、日本の大学をとりまく経済的・社会的環境に大きな変化が押し寄せていたことである。経済的には、日本の大学の粗製濫造と質的低下を許してきた若年人口の高位安定と恒常的大学進学熱の高まり、この二つが同時に崩れはじめたことによって、大学経営に黄信号が点った。また社会的には、(大学がまともな教育に責任を持たなかった結果としての)「レジャーランド」化に対する批判的世論の急速な台頭が挙げられる。
一九七○年代を中心とする例の「大学紛争」は、結果的には、大学の改革に何の実質的成果も収めえなかった反面、大学ならびに大学教授に対する社会的信用を急速に失墜させた。したがって、それ以後大学ならびに大学教授に対する揶揄嘲笑は社会的風潮となった。『文学部唯野教授』(筒井康隆氏の小説。八七年から八九年にかけて季刊「ヘルメス」に連載されて好評を博し、完了後九〇年に岩波書店から出版されるや、忽ちベストセラーとなった)の爆発的成功などは、正にその象徴的出来事であったといえよう。官庁はマスコミに反映される世論に殊のほか敏感だから、こうなると、文部省も動きださざるをえない。
大学をとりまく上記の環境変化の中で、文部省は八七年に文部大臣の諮問機関として「大学審議会」を設置し、いわゆる「大学改革」に本格的に取り組む姿勢を示した。以来十数年、小出しながらも驚くほど速いテンポで出されてきた大学審議会の答申にしたがい、文部省は法制度の改正・改案まで地道に行いながら在来の大学社会の因習を順次克服しようと試みてきた。これを受けて各大学では、概して積極的とはいえなかったが、時代の変化に何とか対応できる内部体制を整備すべく、それなりの自主的努力を重ねはじめた。
このような時期に偶然私のもとに、東京の中堅学校法人である田村学園理事長田村邦彦氏から、多摩地区に設立を予定している小規模な大学プロジェクトへの協力要請が舞い込んできた。同氏と私の共通の友人であった岡昭君(当時、開発銀行副総裁)がかねてからの私の「大学改革論」に共鳴してくれていて、話を田村氏につないでくれたものであった。私の大学改革論は、文部省主導下で進められていた前述の「大学改革」とは、事実上無縁なものであった。もともと一介の技術者を志した私は、学識経験者と称せられる人々が審議会や委員会に連なり、一般的かつ抽象的議論を長々と積み重ねた結果出される答申とか報告書、つまり単なる"総論"の現実的効用を全く信用していない。
私の大学改革論は、私自身の実体験から生まれてきた独自の理念と知識に基づく"各論"である。私が初代学長として八九年に開学した多摩大学はこうした各論の典型的産物であったが、開学とともに次々と打ち出した新しい方式や制度がマスコミを通じて思いがけず過分な世間的評価と知名度を頂戴することになり、時期が時期だっただけに、総論的「大学改革」を先駆ける事例のごとく受け取られた。これには私も痛く恐縮したが、他方この誤解は、全国各地から私への大学新設計画への協力要請となって表れた。率直に言って、当時私に持ち込まれた大学新設計画の多くは私が首をひねらざるをえないものばかりであったが、そのうち幾つかは、私が感心するだけの条件を備えていた。 |